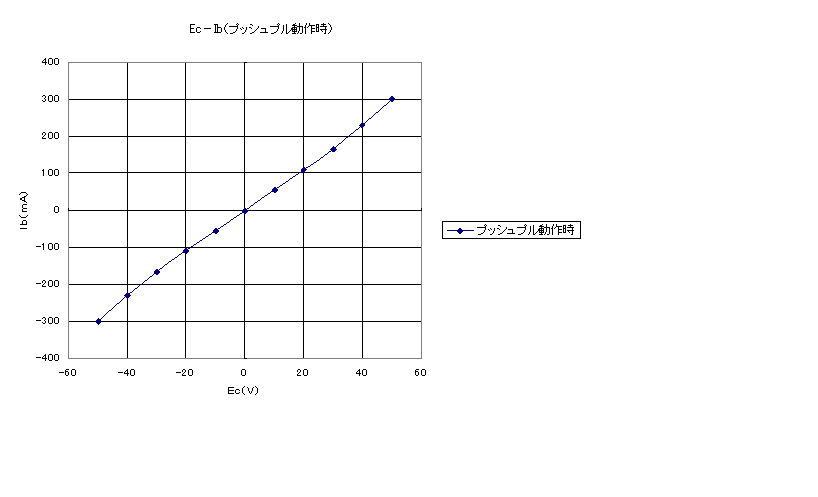手造り真空管アンプの店

手造り真空管アンプの店
プッシュプル合成特性のシミュレーション
真空管アンプを設計するとき、先ず出力管の特性を見てから設計を始める。ここで最大出力が決まり、続いてゲイン、電源回路などが順次決まってくる。この出力管の特性を表しているのが、Vb-Ib特性といわれるグラフである。これは1本の出力管の動作特性を表したグラフであるが、プッシュプルのアンプを設計する時、実際プッシュプル動作したときの特性を示した例が少ないので、プッシュプルの合成特性をシミュレーションで求めた。
図1が6550という出力管のUL接続時のEb(プレート電圧)−Ib(プレート電流)特性である。赤の直線が負荷のロードラインと呼ばれる線で、真空管の動作はこの直線上を動くことになる。シングルアンプはこれで良いのだが、プッシュプル動作の時はこの特性とは異なり、正の半サイクルを受け持つ真空管と負の半サイクルを受け持つ出力管の合成された特性になる。それをコンピューター上でシミュレートした。
図1は6550UL接続時のEb-Ib特性。これは正の半サイクルを受け持つ真空管の特性とすると、(パラメーターはグリッド電圧(Ec))
図2は負の半サイクルを受け持つ真空管の動作を表す。実際は同じ特性で左右上下逆にしてグラフにしたもの。
これらの特性をグラフ上で合成するには動作点を一致させ、これらのグラフを上下合わせたものが図3である。今回の場合は動作点はEb=400V、Ib=50mA、Ec=−50Vとなっており、2つのグラフのEb=400Vの位置を合わせてある。
赤の点線が合成されると予想される合成特性である。
合成は
ー50Vaとー50Vbのグリッド電圧でのIbの値を足す。同様に
ー40Vaとー60Vb
ー60Vaとー40Vb
・・・・・・・・・・・・・・・
と順次対応する合成されるグリッド電圧でのIbを計算する。これらの計算はエクセルの表計算を用いた。
その結果が図4で、これがプッシュプルの合成特性である。
ここで分かることは図1に比べグリッド線が等間隔に並んでいることだ。図1ではグリッドバイアスが深く(グリッド電圧がマイナスに多くなる)につれて電流変化が少なくなっているのが分かる。それに比べプッシュプルでは比較的等間隔に線が並んでいる。
もう少しこの変化を分かりやすく示したのが図5と図6である。
図5は図1のグラフの赤のロードラインでのグリッド電圧(Ec)に対し、プレート電流(Ib)の変化をプロットしたもの。同じように図6は図4のプッシュプル時の合成特性時での赤のロードラインでのEc−Ibをプロットしたもの。
図5では変化が2次曲線に近い形をしている。これは2次歪が多いことを表している。
一方図6ではこれが直線に近くなっている。これはプッシュプルが2次歪をキャンセルしていることを示している。
アマチュアの方の中には、プッシュプルは合成の時に歪が出るから、シングルアンプの方が音が良いと言われる方もおられるようだ。しかしながらこのシミュレーションを見てもお分かりのように、実際にはプッシュプルの方が直線性が良い。
注)今回比較の為、シングル、プッシュプル共負荷抵抗1.25kΩで計算している。実際シングルアンプの時は4倍の5kΩの負荷抵抗になるのでEc−Ib特性は変わってくるが、その傾向に変わりはない。
実際の真空管の特性からプッシュプルの合成特性を求めた例は少ない。原理は理解しても実際どうなっているのという疑問からシミュレーションした。実際の設計では必要ないことだが、動作をより深く理解するには意味があることと思う。
今回6550(UL)という自分が使用している真空管を例に、プッシュプルの合成特性をエクセルで求めてみた。他の真空管も同様に調べてみるのも面白いだろう。これでも分かるようにプッシュプル(UL)の特性は良い。
次回はこの2つのEc−Ibと特性から歪率を計算してみてどの程度歪の差があるか調べてみよう。
真空管アンプは作るのも面白いが、このような別な見方をしていくと、より理解できもっと面白くなる。
参考文献: オーディオ用真空管マニュアル(ラジオ技術社)
パワーアンプの設計と制作(上)(武末数馬 著)
図1:6550のEb−Ib特性(UL接続)
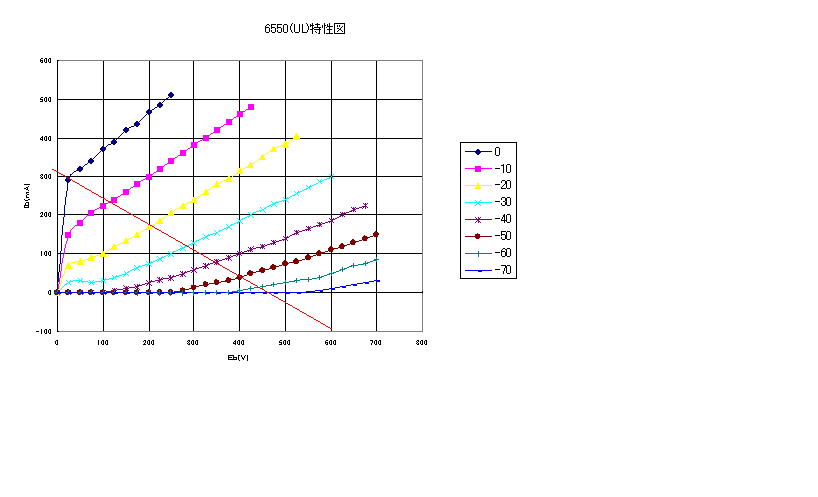
図2:負の半サイクルを受け持つ6550の特性図
図3:グラフの合成
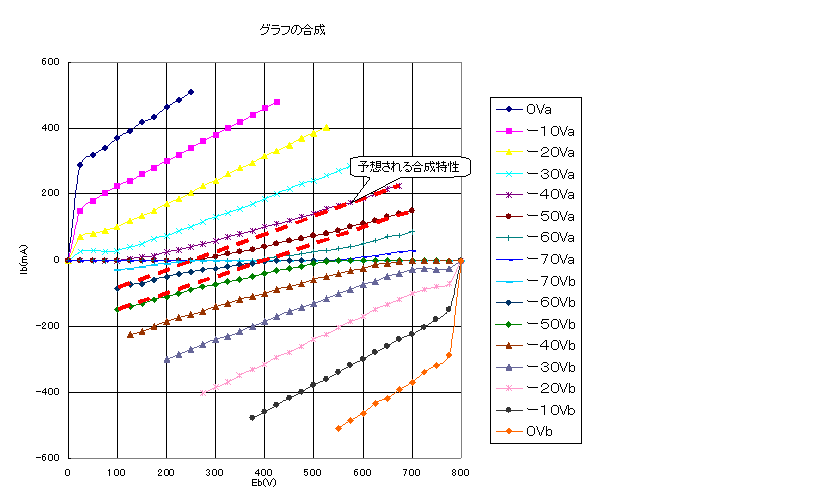
図4:図3のグラフを実際に計算で求めた合成特性(プッシュプルの合成特性)
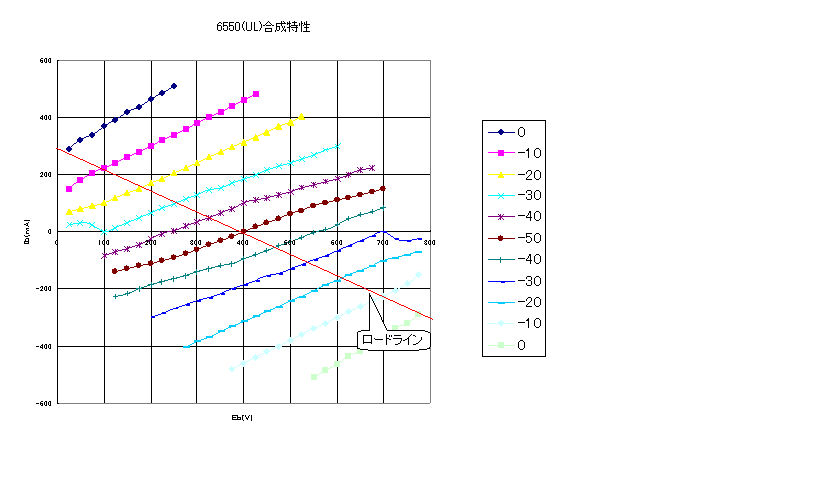
図5:シングル時のEc−Ib特性
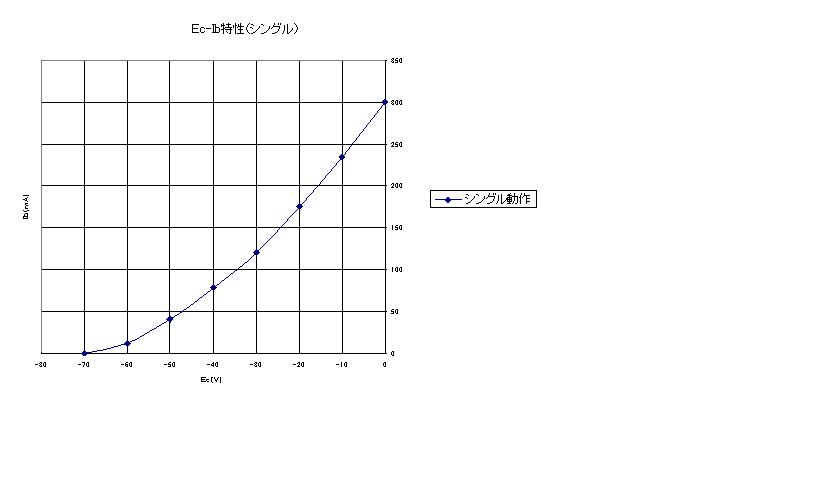
図6:プッシュプル時のEc−Ib特性